学資保険のメリット・デメリットを徹底解説!加入前に知っておくべきポイントを解説

子どもの「教育資金」は、「住宅資金」「老後資金」と並んで「人生の三大資金」の1つとされています。なかでも大学進学時には入学金や授業料、生活費など、まとまったお金が必要になるため、早い段階から計画的に準備しておくことが大切です。
こうした教育資金を計画的に備える方法の1つが「学資保険」です。毎月コツコツと積み立てができる上、万が一の事態にも備えられる点が大きな魅力です。この記事では、学資保険のメリット・デメリットを解説し、加入前に知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。
INDEX
学資保険とは?
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険です。保険料を一定期間支払うことで、子どもの進学時期に合わせて満期金や祝金といった形で給付金を受け取ることができます。
学資保険の保険料は、契約者(通常は親)の年齢や子どもの年齢によって決まります。一般的に、親の年齢が若く、子どもが低年齢のうちに加入すると、保険料は割安になる傾向があります。
また、多くの学資保険には、契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される保障が付いています。さらに、商品によっては、保険料の払込免除に加えて、養育資金として年金形式で給付金を受け取れるタイプもあり、家族の経済的負担を軽減することができます。
このように、学資保険は「貯蓄機能」と「保障機能」の両方を備えており、子どもの将来に向けて堅実に備えるための有力な手段といえるでしょう。
学資保険のメリット
学資保険に加入すると、主につぎのようなメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
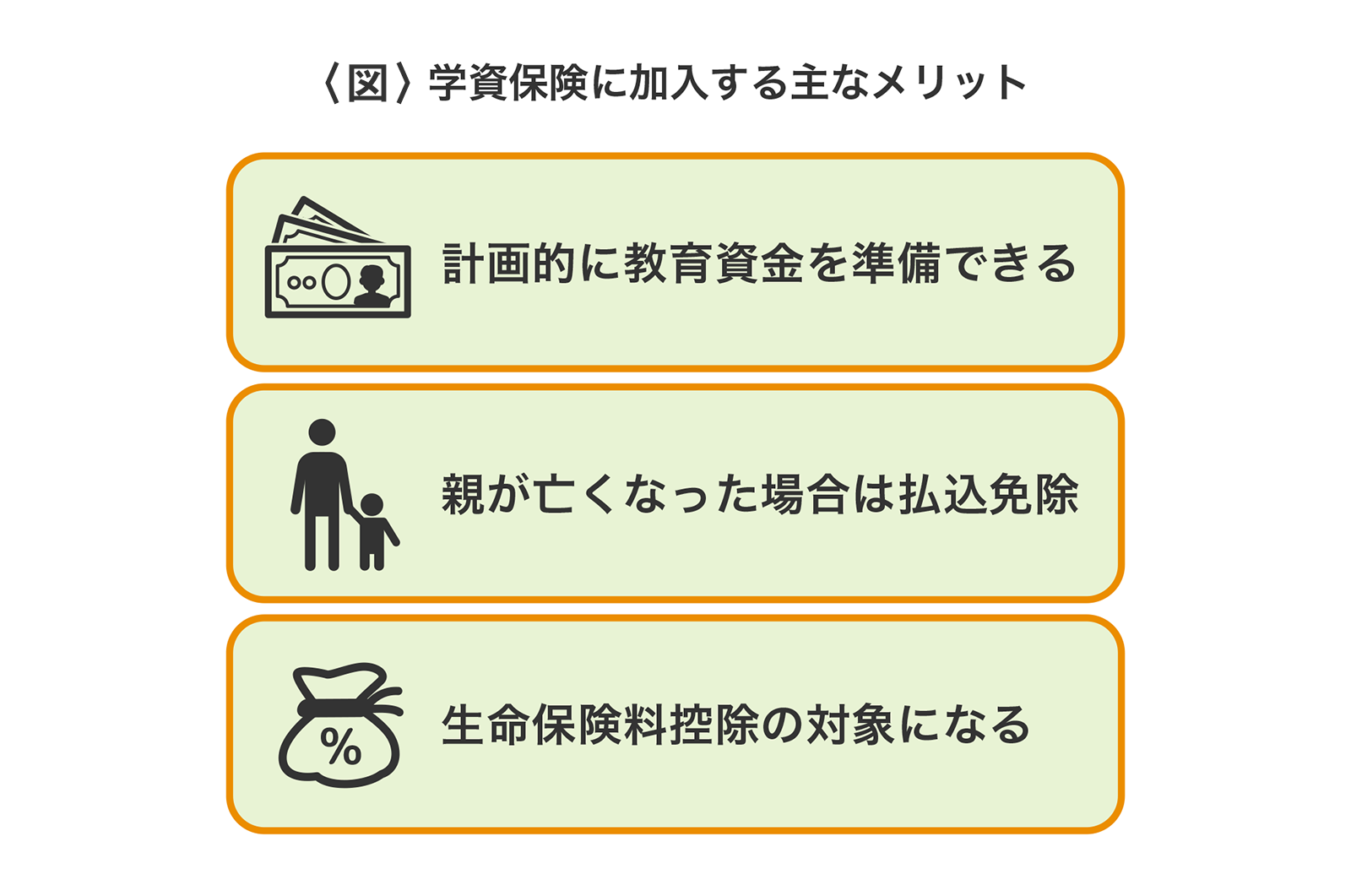
計画的に教育資金を準備できる
学資保険の最大のメリットは、子どもの将来に必要な教育資金を計画的に準備できることです。教育費は子どもが成長するにつれて負担が大きくなり、特に高校や大学ではまとまった金額が必要になります。学資保険なら、教育費が必要なタイミングに合わせて資金を確保することが可能です。
〈表〉高校・大学で必要な教育費の目安(*1)
| 教育費総額 ※高校は3年間、大学は4年間の総費用 |
|
| 公立高等学校(全日制) | 179万円 |
| 私立高等学校(全日制) | 309万円 |
| 国公立大学 | 481万円 |
| 私立大学文系 | 690万円 |
| 私立大学理系 | 822万円 |
- ※高校の教育費は文部科学省「子供の学習費調査」(令和5年度)、大学の教育費は日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」(令和3年度)をもとに算出
また、学資保険は毎月決まった保険料を支払うため、無理なく教育資金を積み立てることができます。預貯金のように途中で資金を取り崩してしまうリスクも少なく、満期までしっかりと教育資金を確保できる安心感も大きな魅力です。
親が亡くなった場合は払込免除
学資保険には、契約者である親が亡くなったり、高度障害状態になったりした場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される「保険料払込免除特約」が付いていることが一般的です。この特約があることで、親に万が一の事態が起きても、子どもの将来に向けた教育資金の準備は継続され、満期金や祝金を予定どおり受け取ることができます。
通常の預貯金では、親が亡くなった場合、そのあとの積立が難しくなり、教育資金が不足するリスクがあります。しかし、学資保険であればその心配がありません。親に万が一のことがあっても確実に資金を確保できる点は、学資保険ならではの強みといえるでしょう。
生命保険料控除の対象になる
学資保険に加入すると、税制上のメリットとして「生命保険料控除」を受けることができます。生命保険料控除とは、支払った保険料の一部が所得控除の対象となる制度で、所得税や住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除には、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの区分がありますが、学資保険は「一般生命保険料控除」の対象となります。年間の支払保険料に応じて、所得税では最大4万円、住民税では最大2万8,000円の控除が適用されます。控除を受けるためには、年末調整または確定申告での手続きが必要です。
教育資金を積み立てるという本来の目的に加えて、税負担の軽減も期待できる点は、学資保険を検討する上で大きな魅力の1つといえるでしょう。
学資保険のデメリット
続いて、学資保険のデメリットも見てみましょう。学資保険には主につぎのようなデメリットがあります。
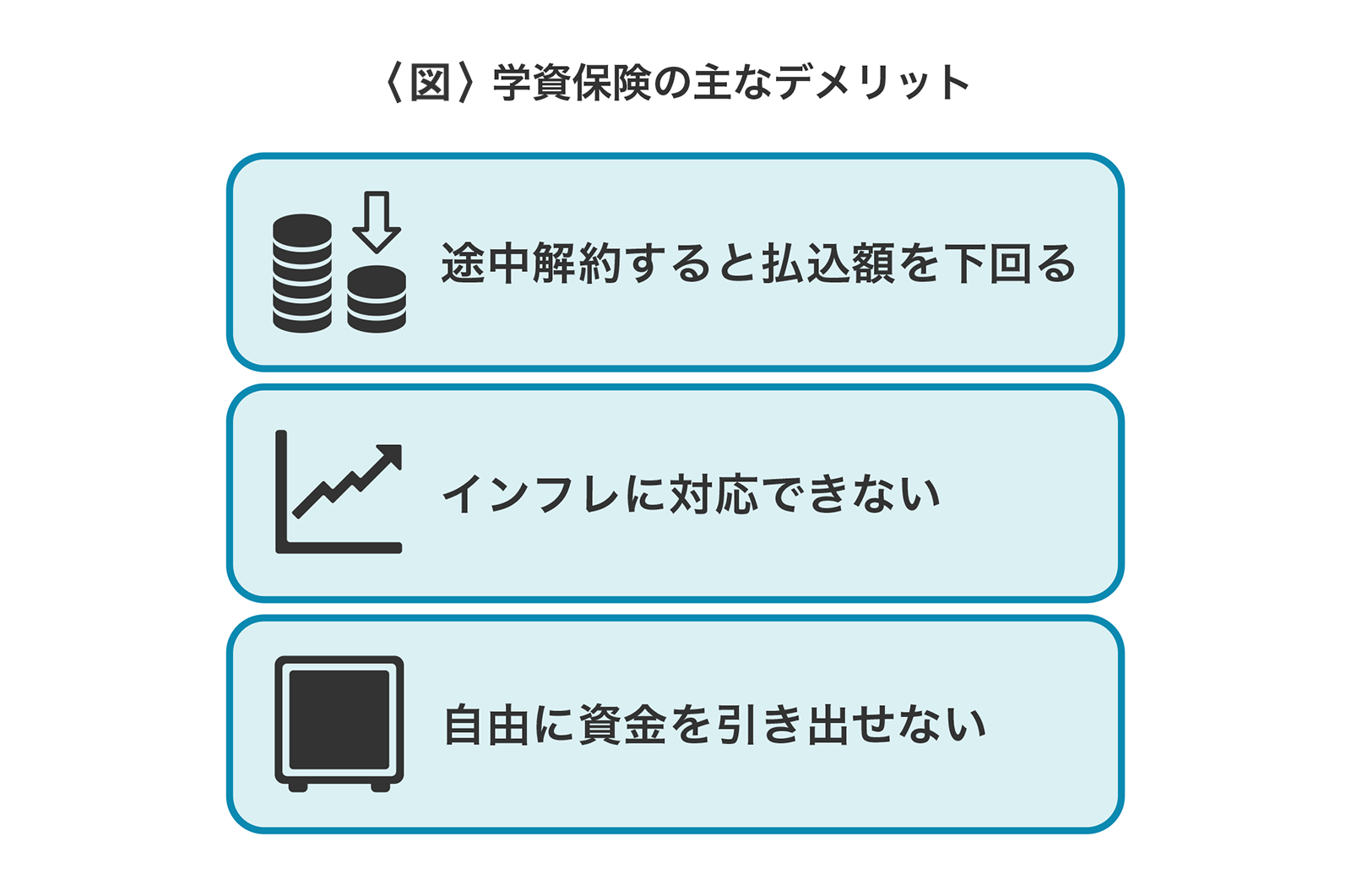
途中解約すると払込額を下回る
学資保険のデメリットの1つは、途中で解約すると多くの場合、「解約返戻金」が支払った保険料の総額を下回ることです。
学資保険は、子どもの進学時期に合わせてまとまったお金を受け取ることを目的に、長期的に資金を積み立てていく商品です。そのため、予定より早く解約してしまうと、保険会社が十分にお金を運用できず、その分戻ってくる金額が少なくなってしまいます。特に、契約から間もない時期に解約すると、支払った保険料を大きく下回るリスクが高くなります。
このような性質から、学資保険を検討する際には「途中で解約する可能性があるかどうか」をしっかり見極めることが大切です。ライフプランや家計状況に合った無理のない保険設計を心掛けましょう。
インフレに対応できない
学資保険は、契約時に将来の給付金額があらかじめ決まっていることが多いため、将来的にインフレが進んだ場合、受け取る金額の「実質的な価値」が目減りしてしまうリスクがあります。
たとえば、満期金として200万円を受け取れるように設定していたとしても、20年後に物価が上昇していたら、その200万円で購入できる商品やサービスの量は減ってしまいます。そうなると、想定していたほどには教育費や生活費をまかなえない可能性があります。
学資保険は、将来決まった金額を受け取れる安心感がある一方で、インフレには弱く、経済状況の変化に対応しにくい商品であることは知っておきましょう。
特に近年、大学の学費は上昇傾向にあります。今後もこの傾向が続くと考えられることから、将来の学費の値上がりを見据えた備えが重要になってきます。「貯めたはずなのに足りない」とならないように、投資信託などインフレに強い金融商品との併用を検討してもよいでしょう。
自由に資金を引き出せない
学資保険には、契約期間中に自由に資金を引き出すことができないというデメリットもあります。契約時に定めたタイミング以外ではお金を使うことができないため、急な出費や家計の変化に対応しにくい点は注意が必要です。
急にまとまったお金が必要になった場合、学資保険からの引き出しはできず、解約という選択肢を取らざるを得ないケースもあります。しかし、前述のとおり、途中解約すると解約返戻金が支払った保険料の総額を下回る可能性があります。
解約返戻金を担保として保険会社からお金を借りる「契約者貸付制度」を利用できる学資保険もありますが、これはあくまで借入れであり、返済時には利息の支払いが必要です。加えて、一定額以上の保険料が積み立てられていなければ利用できないなどの条件もあります。
そのため、急な資金ニーズに備えて、預貯金など流動性の高い資産も併せて確保しておくことが望ましいでしょう。
学資保険がおすすめな人
それでは、どのような人が学資保険に向いているのでしょうか。学資保険のメリット・デメリットを踏まえると、学資保険をおすすめできるのはつぎのような人です。
学費を計画的に貯めたい人
学資保険は「教育資金を計画的に貯めたい人」にとって有効な選択肢です。教育費は子どもが成長するにつれて負担が大きくなります。特に、大学進学時には、入学金や授業料に加えて、1人暮らしをする場合はアパート代や生活費など多額の資金が必要になります。そうした将来の大きな出費に備えるためには、日々の生活の中で無理なく、かつ確実にお金を積み立てていくしくみが必要です。
学資保険は、毎月決まった保険料を支払うことで、自動的に教育資金を積み立てられるしくみになっています。契約時に受取時期や金額を設定できるため、資金計画が立てやすく、教育費が必要なタイミングに合わせてお金を準備できます。また、自分の意思で積み立てたり取り崩したりできる預貯金とは違い、強制的に積み立てられ、自由に引き出すことはできないため、計画的な貯蓄が苦手な人にも向いています。
子どもの将来を見据え、着実に教育資金を準備したいと考える人にとって、学資保険は堅実で安心感のある手段といえるでしょう。
万が一にも備えたい人
子どもの教育資金を準備しながら、「万が一にも備えたい人」にとっても、学資保険は心強い選択肢となります。
前述のとおり、学資保険には、契約者である親が死亡または高度障害になった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される「保険料払込免除特約」が付いていることが一般的です。保険料を支払わなくても契約はそのまま続き、満期金や祝金を予定どおり受け取ることができます。
予期せぬ出来事で家計が苦しくなった場合でも、子どもの教育資金をしっかりと確保できることは、親にとって大きな安心材料です。これは、「貯蓄機能」と「保障機能」を兼ね備えた学資保険ならではの特徴といえるでしょう。
「自分に何かあっても、子どもにはできる限りの教育を受けさせてあげたい」と願う人にとって、学資保険は頼もしい味方となります。
学資保険を利用して計画的に学費を用意しよう

学資保険は、「貯蓄機能」と「保障機能」の両方を兼ね備えており、子どもの教育資金を準備しながら、親の万が一にも備えられる点が魅力です。また、「生命保険料控除」の対象となるため、税制上のメリットも期待できます。
一方で、途中で解約すると、支払った保険料の総額よりも少ない金額しか戻ってこないリスクがあるほか、インフレに対応しづらいといったデメリットもあります。
こうした特徴をしっかり理解した上で、預貯金やほかの金融商品との併用も視野に入れながら、自分のライフプランに合った方法で教育資金を備えていくことが大切です。
おすすめ商品
保険の選び方に迷われた際は、お気軽にご相談ください。
“どんな保険を選んだらいいかわからない”
“ぴったりの保険を教えてほしい”
そんなあなたのギモンにお答えします!
分かりやすいパンフレットを
お取り寄せ
経験豊富な「保険の専門家」をご紹介



